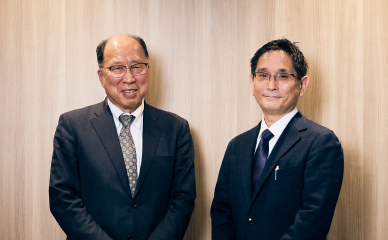農林中金バリューインベストメンツ(NVIC)は、2014年10月の設立から10年を迎えました。本シリーズ「NVIC History」では、その歩みを振り返り、未来への指針を探っていきます。
第3回となる今回は、設立時の初代社長(Founding CEO)を務めた髙橋さんを迎え、NVIC創業の舞台裏から、後年に手がけたGPIFのポートフォリオ改革に至るまでを語っていただきました。対談では、奥野との率直なやりとりのなかに、髙橋さんの哲学とユーモア、そして未来への眼差しがにじみ出ています。NVICがいかにして生まれ、何を大切にしてきたのか。その原点を、ぜひ感じ取っていただければ幸いです。
1980年農林中央金庫入庫。債券投資部長、開発投資部長などを経て、2007年常務理事、2011年専務理事。年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF) 元理事長。
1992年日本長期信用銀行入行。長銀証券、UBS証券を経て2003年に農林中央金庫入庫。2007年より「長期厳選投資ファンド」の運用を始める。2014年から現職。
NVICは、2024年10月にお陰様で設立10周年を迎えました。この記念すべき機会に、「NVIC History」と題し、NVICの成長にご尽力いただいた皆様をゲストにお迎えし、お話を伺っております。今回は、まさにNVICの誕生、会社設立という最大の出来事の中心人物である、初代社長の髙橋さんにお越しいただきました。2014年当時の様々な出来事について、深くお話を伺いたいと存じます。

髙橋さんのご経歴を簡単にご紹介いたします。
農林中金で専務を務められ、その前の開発投資部長時代から、私はご一緒にお仕事をさせていただきました。髙橋さんが専務の時代にNVICが設立され、以降、農林中金のNo2、専務職の方が非常勤ながら社長を担っていただくという形となりました。NVICは2014年10月の設立ですが、農林中金としてその前に子会社を設立したのは、農中信託銀行まで遡るそうです。農中信託銀行の設立は、NVIC設立の19年前とのことです。
長らく新たな子会社設立がなかった農林中金において、NVIC設立の決断に至った背景や、ご尽力された点について、まずお聞かせいただけますでしょうか。
金融機関である我々は、単年度での業績評価が基本であり、また金融庁の監督下にもあります。そのような状況下で、一部門とはいえ、株式の長期投資に本格的に取り組むことは、既存の組織体制では難しい側面がありました。株式投資の特性として、良い企業を見つけて投資が成功しても、その利益が短期的な業績目標達成のために活用されてしまう、いわゆる「益出し」に使われる傾向がありました。これは、長期的な視点での投資活動を阻害する要因となります。
また、投資のサイクルは会計年度とは全く異なります。3月を迎える頃には、利益または損失を計上する必要が生じ、損失が必要な時期には株式の活用が制限され、債券で調整するという慣例がありました。株式は、短期的な利益が必要な時のみに活用されていたのです。若かりし頃の私も、そのような慣行に抵抗を試みましたが、最終的には組織の一員として受け入れざるを得ませんでした。

このような状況が続く中で、奥野さんが長期投資への情熱を持ち続けていることに感銘を受け、農中信託銀行への異動をお願いしたのです。組織が変われば、多少なりとも状況が改善するのではないかと考えましたが、農中信託銀行もまた、会計年度による業績評価の枠組みの中にありました。結局、既存の大きな組織の中では、長期的な視点での株式投資を本格的に行うことは難しいと痛感しました。
それに加え、将来を見据えた時、奥野さんの卓越した才能を活かし、長期的な株式投資にしっかりと取り組むことができる環境を創りたいという強い思いがありました。メガバンクや生命保険会社においても同様に、本体では株式は短期的な利益確保の手段として用いられ、真の長期投資は困難な状況でした。そこで、農中信託銀行という枠組みを超え、独立した組織を設立することが最善の策だと考えたのです。短期的な業績評価に左右されることなく、真に価値のある株式に長期投資を行うための独立した組織、それがNVIC設立の原点です。
組織の壁を越えて
そのような背景の中、実際に組織を動かし、意思決定を進めていく上で、どのような困難がありましたでしょうか。
率直にお話しさせていただきますと、組織において、前例のない新しいことを行うには、様々な壁が存在します。農林中金にとって、「ヘンなこと」、つまり従来の慣習や考え方から逸脱することは、関係者への説明責任という点で大きなハードルとなります。「独立した投資会社を新たに設立する」という提案は、農協の皆様にとって、直接的なメリットが見えにくいものでした。「それが農協にどういう良いことがあるのだ?」という疑問が生じるのは当然のことです。

時間をかけて丁寧に説明すれば、中長期的な視点で見れば、農協組合員の皆様の資産形成に必ず貢献できること、そして投資を通じて得られる企業経営の視点は、組合員の皆様の農業経営にも有益であることをご理解いただけると信じていました。
しかしながら、長期的に正しいことが、短期的に理解を得られるとは限りません。農協の組合長の方々は大変お忙しく、十分な時間を割いてお話を聞いていただくことが難しい場合もあり、「結局、何が言いたいのかよくわからない」という反応になってしまうこともありました。理事長をはじめとする役員の方々にご説明する際も、もし私が逆の立場であれば、「面倒なことを持ち込んできたな」と感じたかもしれません。
ですから、「面倒だな」と思わせないために、どのように説明し、どのように進めていくかに、細心の注意を払いました。組織にいれば誰もが理解できると思いますが、提案内容そのものの正当性は当然のこと、想定される質問とその模範解答を周到に準備し、あらゆる角度からの反論に対応できるようにしておくことは基本です。その上で、さらに重要なのが、誰から根回しをするか、いつ頃から始めるか、時には誰を敢えて後回しにするかといった、戦略的な判断です。これは非常に難しい判断が求められます。そして最終的には、一部の方々の反感を買うことも覚悟しなければ、事を成し遂げることはできません。
世の中には、敢えて相手を不快にさせなければ実現できないこともあるのです。しかし、そのようなことを繰り返していると、組織の中で円滑な人間関係を築くことは難しくなり、結果として自分のやりたいことを実現できなくなる可能性もあります。ですから、普段は極力避けるべきですが、「ここが勝負だ」という場面では、断固として行動する覚悟が必要でした。そして、そのようにして設立されたのが、NVICです。
当時、髙橋さんの下でこのプロジェクトに携わることができたのは、サラリーマンとしての私の幸運だったと改めて感じています。髙橋さんの卓越したリーダーシップのもと、金丸さん、尾崎さんといった素晴らしい方々とご一緒できたのは、まるで惑星直列のような、極めて稀な幸運だったと思っています。本当に、良い時代に、良い場所にいられたと感謝しています。

最終的には、理解のある方々に恵まれた、ということに尽きると思います。自由に意見を言い合える風土も、農林中金の大きな魅力です。仕事は、自分の思い通りにならないからこそ、上手くいくものだと私は考えています。一人で進めていたら、必ずどこかで間違ってしまうでしょう。様々な意見や批判に耳を傾け、そこで立ち止まって考えることが重要なのです。単に多数決で決めるのではなく、お互いが言いたいことを言い合い、より良い結論を導き出すことが大切です。
まもなく67歳になりますが、つくづく「時間」の重要性を感じます。1ヶ月経てば、状況や見え方が全く変わることが少なくありません。目先の時間に追われて性急に結論を出すのではなく、多少時間をかけてでも、じっくりと考えること。投資も同様だと思いますが、「ここで決めてしまって本当に良いのか」と、判断の前に立ち止まることも、時には非常に重要なことだと感じています。
3Mとの出会い
そのような髙橋さんの英断があってこそ、農林中金にとって久しぶりの子会社、NVICが誕生したわけですね。今でもよく話題に上るのが、2015年2月の設立セミナーでのエピソードです。セミナーでは、信越化学工業の金川さんに基調講演をお願いいたしました。その際、宮園さん(当時、副理事長であり、髙橋さんの後にGPIF理事長となられた方)が、NVICのことを「ウチにもついに孫ができた」と、愛情たっぷりに仰ってくださったことが、今でも忘れられない、心温まる思い出です。宮園さんをはじめ、多くの方がNVICの誕生を温かく見守ってくださっていたのだと、改めて感謝の念が湧き上がります。
もちろん、その温かい眼差しは今も農林中金の中に息づいていると感じていますし、農林中金はNVICにとって、かけがえのない母体であり、共に成長を目指す重要なパートナーです。プロフェッショナルファームとして、農林中金にはない強みをNVICが備え、高めていく必要はありますが、農林中金との強固な連携こそが、NVICの最大の強みだと確信しています。
それが設立の日の記憶に残るエピソードなのですが、NVICにとって非常に大きな転機となったのが、アメリカの3Mへの訪問でした。現在では、10年以上投資を継続している企業もあるため、投資先のCEOがオフィスを訪問してくださることもありますが、当時のNVICはまだ設立間もない、駆け出しの運用会社でした。
その当時、3MのIR担当の重役であったマット・ギンター氏との間で、非常に興味深い対話ができたことが大きかったと思います。「今度ミネソタに来てくれたら、CEOのインゲ・チューリンとのアポイントをセッティングするよ」という、信じられないようなお話をいただくことができたのです。3Mは時価総額10兆円を超える巨大企業ですから、そのCEOにお会いできるのであれば、ぜひ髙橋さんにご同行いただきたいと考え、お電話したところ、第一声が「行くぞ」だったのです。そして、髙橋さんと尾崎さんもご一緒して、ミネソタの3M本社を訪問することになりました。
3Mは本当に素晴らしい会社です。テクノロジーイノベーションセンターは圧巻でした。
実は、おおぶねの年次総会で、受益者の皆様を日本のテクノロジーイノベーションセンターにご案内したのですが、皆様大変喜んでくださいました。そのような機会を設けることができたのも、長年にわたり3Mとの良好なコミュニケーションと信頼関係を築き上げてきたからに他なりません。そして、その礎を築く上で、あの時、髙橋さんがご一緒してくださったことが、非常に大きかったと感じています。
3Mでは、非常に気さくな方が出てこられましたが、それがCEOのインゲ・チューリン氏でした。そこで、非常に印象深い発見がありました。それは、圧倒的に内部からの昇進が多く、長年勤めている方が重要なポジションに就いている、ということでした。これは良い悪いという話ではなく、私自身、アメリカの企業はもっとドライで、個人のキャリア意識も高く、人材の入れ替わりも激しいのではないかと想像していました。

しかし、お会いしたほとんどの方が「20年前から3Mで働いている」というように仰っており、日本の会社に近い印象さえ受けました。個人のキャリア形成のためには、労働市場の流動化が良いとか、転職を重ねてキャリアを積んだ方が良いと言われることもありますが、それは一面的な見方に過ぎないと思います。組織として考えると、長く勤めている人が多い方が上手くいく分野やビジネスもあるはずです。個人のレベルで見ても、長く勤めることでやりたいことができる場合もあれば、転職することで新たな道が開ける場合もあります。ただ、「キャリアアップ」とか「やりがい」といった言葉は、時に実態を伴わないこともあります。
本当に言えることはただ一つ。後で振り返った時に後悔しない、それだけです。「あの時、やっておけばよかった」と後悔するかもしれないと思ったら、やるべきです。それを「やりがい」とか「キャリア」と呼ぶのかもしれません。現代の日本においては、ある程度のお金があれば生きていくことはできます。だからこそ、その時その時、後で振り返った時に後悔しないような決断をすることが大切です。60歳を過ぎて、つくづくそう感じています。
髙橋さんが、後悔されることはありますか?
しょっちゅうありますよ。後悔のほとんどは、「もう少し相手に気を遣えばよかったかなあ」ということです。例えば、もう少し優しい言葉をかけていれば、とかね。でも、それを口に出してしまうと、私のキャラクターが少しばかり軟弱になってしまうので、言わないでおきますけれど(笑)。
GPIFポートフォリオ改革
当時のGPIFのポートフォリオは、6割が日本国債で、外国債券と株式を合わせても2割程度でした。当時、私は「このままでは、自分の年金も危ない」と強く感じました。日本国債6割という比率は、当時の金利が1%程度であったとしても、決して十分とは言えませんでした。国債の比率を減らし、株式の比率を増やすという改革案には、まず財務省が反対。さらに、外国株式の比率を増やすことには、経団連が反対。そのような反対を受けながらも、現在のGPIFの資産配分は、国内債券、外国債券、国内株式、外国株式が、ほぼ1/4ずつとなっています。
高橋さんがGPIF理事長にご就任され、株式の比率が半分になったのですね。もしあのタイミングで株式の比率を引き上げていなければ、大変な事態になっていたでしょう。

GPIF理事長を務めてみて、つくづく感じたことがあります。それは、「正しいことをすれば良い」という単純なものではないということです。人間には感情があります。正しいことだからといって、それまでの行動や考え方をすぐに変えられるものではありません。それは当然のことでしょう。それぞれが背負ってきた人生や歴史があるのですから。GPIFには、私よりも年上の部長や管理職の方々がいらっしゃいました。しかも、ご自身のこれまでの仕事に誇りを持っておられる。日本国債をしっかりと安いところで買って、確かにそれはきちんとしたポートフォリオだったのです。
それが、突然現れた人間から「はい、この3分の1は売却します」と言われるわけです。それは、彼らのこれまでの人生を否定するようなものでしょう。改革とは、それまで積み上げてきたものを否定することでもあるのです。しかし、時には否定しなければならないこともあるのです。敢えて悪者になる。そのような役割は、極力避けるべきなのですが。
イーロン・マスク、ラリー・フィンクとの邂逅
GPIFでのご苦労は、ここまでお話しいただいたことが最も大きかったということになりますでしょうか。
そうかもしれません。しかし、面白いこともたくさんありました。
イーロン・マスク氏が来訪されたこともありました。いつの間にかGPIFがテスラの筆頭株主の一つになっていたのです。それで、マスク氏が中国からの帰国の途中にGPIFに立ち寄られたのです。その時感じたのは、彼はEVそのものにはあまり関心がないのかもしれない、ということでした。彼の真の関心は、火星に行くことなのだと感じました。ですから、「テスラという会社は本当に大丈夫なのだろうか?」とさえ思いました。しかし、彼の素晴らしい点もあり、何か問題が発生すると、すぐにマスク氏本人と側近の幹部たちが直接対応するそうです。とはいえ、マスク氏の関心の半分以上は、SPACE Xや火星に向けられているように感じました。とんでもない人物だと感じると同時に、世の中を変えるような人物というのは、ああいう類の人なのだろうとも思いました。
GPIF理事長を務めて良かったことの一つは、日本の皆様の大切な年金資金でGPIFが株主となり、世界的な企業のトップの方々が、わざわざ私たちに会いに来てくださったことです。ブラックロックのラリー・フィンク氏などは、年に3回ほど来訪されます。私は特に親しい付き合いをしているつもりはありませんが、彼は私のことを「友達だ」と言うのです。リーマンショック後、2008年、2009年の金融危機で経営が悪化した様々な会社の不良資産(デリバティブを含む)を一時的に引き受け、整理・流動化する仕事を、アメリカの連邦準備制度理事会(FRB)から請け負ったのがブラックロックでした。その結果、彼らの運用資産は4倍ほどに膨れ上がり、そこで急成長を遂げたのです。
フィンク氏は私に、「髙橋さん、ブラックロックは急速に資産規模が拡大しましたが、それに伴う人材育成が追いついていません。懸命に採用活動を行っていますが、資産のボリュームに人材が対応できていないのです。JPモルガンやゴールドマン・サックスは優秀な人材が豊富ですが、資産規模はそれほど大きくありません。しかし、ブラックロックはその逆なのです。それが、私の悩みです」と打ち明けてきました。その話を聞いて、私はこの人物は誠実な経営者だと感じました。

ちゃんとやっていれば集まる、それが理想
今の日本の運用業界に対して、どのような感想や、こうあるべきだという理想像をお持ちでしょうか。
率直に申し上げますと、GPIFを退任した後、多くの会社からお誘いをいただきました。その中で、運用業界には「お金に対して潔癖ではない人が少なくない」と感じました。お誘いの内容を聞くと、結局のところ「GPIF理事長」という肩書を利用して、海外の投資家から資金を集めようという話が多く、ある程度の報酬を支払えば、私がその役割を担ってくれると考えているようでした。「他の候補者は既に承諾していますよ」などと言って誘ってくるケースもありました。このような話が、想像以上に多いことに驚きました。この運用の世界に身を置く際には、相手が何を考えているのか、なぜ自分に話を持ちかけてきたのか、そうしたことを冷静に分析する必要があると感じています。
お金を集めることが中心になっているのかもしれません。私たちにはそのような潤沢なリソースはありませんが、「売らんかな」という姿勢でビジネスを行うことは、創業以来ありません。「こうすれば資金が集められるのではないか」という発想は全くなく、むしろ、私たちが真摯に、そして誠実に業務に取り組んでいれば、自然と資金は集まってくると考えています。それが、他の運用会社との大きな違いだと感じています。もちろん、設立の経緯が異なるという背景もあると思いますが。
ちゃんとやっていれば集まる、それが理想ですよね。2018年、2019年頃を振り返ると、個人投資家、特に若い世代の方々が、これほどまでに株式を保有するようになるとは想像もできませんでした。私が良いと思うのは、日本の株式だけでなく、海外の株式も保有している人が増えていることです。これは非常に良い傾向です。日本一国だけで、私たちは生きていくことはできません。自分の資産の中に海外の資産を持つことが、当たり前のことになっていけば良いと思います。
金融教育の前にデジタル社会を生き抜く羅針盤を

そのような流れの中で、金融教育の重要性は増すばかりです。髙橋さんは、この複雑な時代において、金融教育はいかにあるべきだとお考えでしょうか。
今、私たちは情報の奔流の中に生きています。特にデジタル領域においては、真偽不明な情報や、人々の感情を煽るような言説が溢れており、それらに対する抵抗力を養うことが喫緊の課題だと感じています。金融の世界も例外ではありません。「必ず儲かる」といった甘い誘いの裏には、危険が潜んでいることも少なくありません。

もちろん、国による規制や第三者機関によるファクトチェックは重要ですが、最終的に頼るべきは、一人ひとりの情報を見抜く力、すなわち情報リテラシーです。金融教育という名の下に、複雑な金融商品の知識を詰め込む前に、もっと根源的な教育が必要だと考えます。それは、自身が発信する情報、そして受け取る情報が、どのように社会に影響を与えるのかを理解すること。インターネット上でのやり取りの裏側で、どのような仕組みが働き、どのような意図を持った人々が存在するのかを知ることです。
小学校中学年くらいの早い段階から、デジタルツールを用いた疑似体験を通じて、画面に表示される情報が必ずしも真実とは限らない、都合よく作られたものである可能性がある、ということを肌で感じて学ぶべきです。私も、日々多くの情報に触れますが、その真偽を見抜く術を持たなければ、容易に誤った方向に導かれてしまうでしょう。従来の金融教育でイメージされるような、株や債券のリスクとリターンの関係といった知識も重要ですが、若い世代が最初に触れるのは、多くの場合、「簡単に儲かる」といった誘惑でしょう。だからこそ、そのような誘いが、どのような人々によって、どのような意図を持って発信されているのか、その構造を早い段階で理解させることが重要なのです。その上で初めて、金融商品の本質的な知識を学ぶ意味が出てくるのだと思います。
まさにこの1年で、AI技術は驚異的な進化を遂げ、真実と虚構の境界線は曖昧になるばかりです。
今や、大学生が普通に株を持っている時代になりました。これは素晴らしい変化だと思います。しかしその一方で、悪意のある広告も巧妙化しています。そうした情報がどのように作られ、拡散していくのか、そのメカニズムを知る教育が不可欠だと感じています。
金融教育の前に、「ファクト」をどのように確認するか、という根源的なスキルを身につけることが重要ということですね。
ファクトの確認も重要ですが、例えば、オンライン広告の表示順位を決定するアルゴリズム。それがどのような関数や方程式で成り立っているのか、一般の人が理解することは難しいでしょう。簡単なものでも良いので、実際にそのようなアルゴリズムを自分で作ってみる経験を通じて、情報の背後にある構造を理解できるようになるはずです。
金融商品としての株についての教育が必要だとは、私自身は考えていません。
私も全く同感です。
株は、企業の経済活動が生み出す価値の派生商品に過ぎません。したがって、企業活動の意義、そしてその結果として現れる財務諸表などの数字を理解できなければ、株の本質を理解することは不可能だと考えています。株価の変動だけを見ていても意味がない、それが私たちの金融教育における重要なメッセージの一つです。

そのような本質的な教育を、多忙な学校の先生だけに委ねるのは、酷であり、現実的ではありません。ここにこそ、NVICの役割があるのではないでしょうか。教員の専門性を高めるというアプローチもありますが、もし私が教員であれば、それは大きな負担に感じるでしょう。「一体、何を、どう教えれば良いのか?」と途方に暮れてしまうかもしれません。現代の子どもたちは、皆スマートフォンを持ち、情報に溢れた環境で育っています。時には、「先生、言っていることが嘘だ!」と指摘することさえあるでしょう。やはり、皆様のような金融のプロフェッショナルが、アプリや動画教材などを通じて、先生方をサポートしていく必要があると思います。先生方は本当に忙しいのですから、先生方を支えることが、結果的に子どもたちの未来を拓くことになるのだと信じています。
NVICとして、その重要な役割をしっかりと担ってまいります。
質疑応答
Q. GPIF理事長時代、日本国債から株式へシフトさせた際、易きに流れず変革を成し遂げられた心の灯火は、どのような想いでしたか?
率直に申し上げますと、実はそれほど大層なものではありませんでした。
農林中金で専務、JA三井リースで社長を務めさせていただいた経験から、地位や名誉に対する執着は薄れていました。極端な話、次の日に解任されても生活に困るわけではありません。GPIFの伝統や文化を否定しようなどとは全く考えていませんでしたし、私も様々な情報を収集し、時間をかけて深く考えました。「今がそのタイミングなのか?」と自問自答も繰り返しました。しかし、当時の日本国債の金利はほぼゼロであり、これ以上待つことはできないと考えました。日本株も外国株も、ここで投資しなければ、もうチャンスはないだろうと。高くなってからでは、購入することは難しくなります。一部の方々から批判を受けることも覚悟していました。JA三井リースの社長を辞任する際には、多くの関係者から叱責を受けました。
そのような経緯でGPIFに来た以上、年金を受け取るのは国民の皆様ですから、ご迷惑をおかけした方々に対して、何らかの形で恩返しをしたいという強い気持ちがありました。「正しいことをやり遂げるために、捨て身の覚悟で断行した」というような、劇的なものではありません。むしろ、ある程度の経験を積ませていただいたことで、「まあ、いいか」という、ある種の達観の境地に至っていたのかもしれません。「まあ、いいか」の中には、GPIFの古参の職員の中には、生涯理解し合えない人もいるかもしれない、それも「まあ、いいか」という気持ちも含まれていました。もし、GPIFの職員の方々と長年一緒に仕事をしていたら、このような大胆な改革は難しかったかもしれません。
しかし、私がGPIFに来て半年ほどの頃でしたので、比較的スムーズに行動に移すことができました。翌年にはBREXITが発生しました。「理事長、もう株式の購入はやめましょう」という進言もありましたが、「このような千載一遇のチャンスはない。天が与えてくれた奇跡だ、買いなさい」と指示しました。1日の購入額は500億円と上限があったため、私の言葉の勢いほどには株式は増えませんでしたが。その後、トランプ大統領が誕生し、「さあ、これから買うぞ」と思っていたら、株価が上昇してしまいました。とにかく、「理事長、株式の購入はやめましょう」という進言を何度も受け、「理事長は本当に株がお好きですね」と、よく言われたものです(笑)

あとがき
今回の対談を通じて、NVICという組織がなぜ生まれ、何を大切に歩んできたのか、その根にある哲学を改めて見つめ直す機会となりました。「後悔しない選択をすること」。髙橋さんのこの言葉には、変化を恐れず、信念をもって前に進むことの意味が凝縮されています。
また、組織に必要なのは、立場を超えて意見を交わし、対話からより良い解を導き出す文化であることも伝わってきました。10年という節目を迎えた今、NVICが次に目指すべき未来をどう描くのか。今回の対話は、その方向性を考えるうえで大きな示唆を与えてくれました。これからも、私たちは実直に、そして丁寧に、価値と向き合い続けていきます。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。