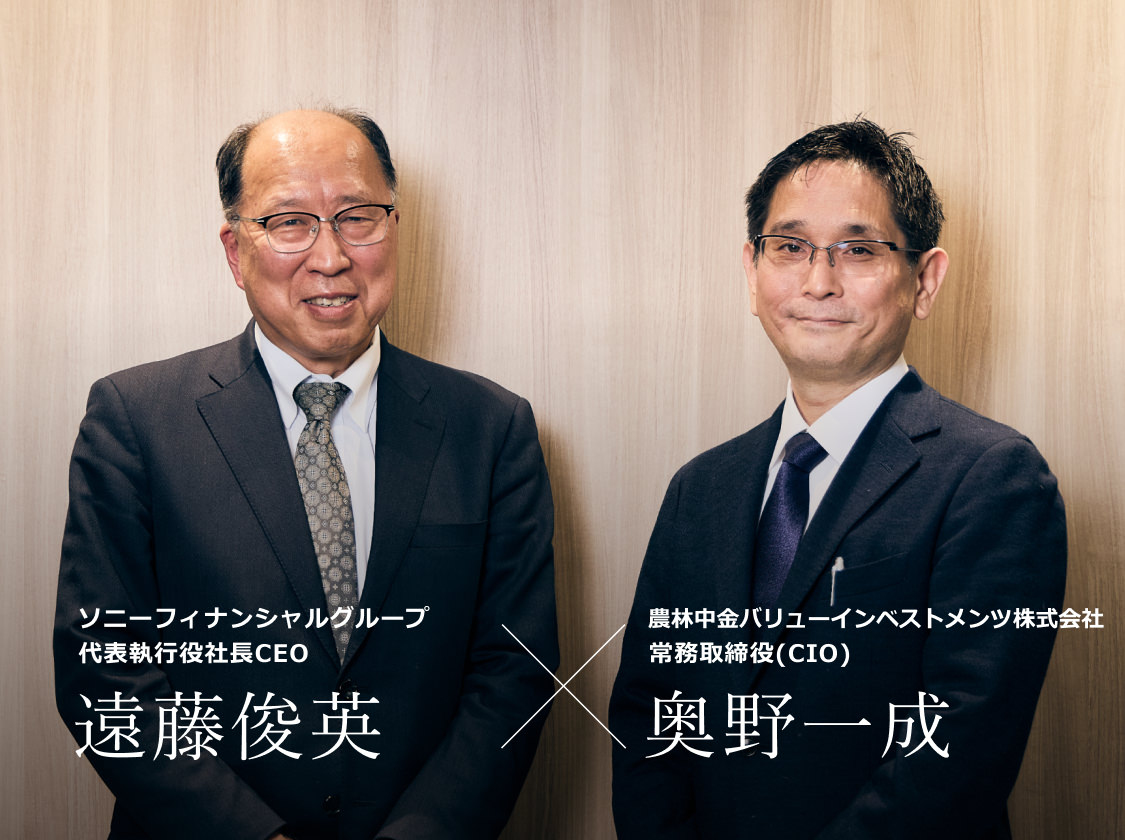10年前にスタートした農林中金バリューインベストメンツ(NVIC)。その歩みを振り返り、これからの進化の方向性を考えるにあたり、私たちは改めて「原点」に立ち返る必要があると感じています。今回お迎えしたのは、元金融庁長官であり、現在はソニーフィナンシャルグループ 代表執行役社長CEOとして活躍されている遠藤さん。コロナ禍の中でも京都大学での講義や地域視察など、多方面で私たちの活動と交差してきた方です。
対談では、「企業哲学をどう根づかせるか」「現場で本当に意味のある金融教育とは何か」「顧客本位のサービスとはどうあるべきか」そんな問いを軸に、遠藤さんと奥野が率直に語り合いました。表面的な制度の話にとどまらず、金融行政の裏側や組織文化の本質、そして日本の未来に対する想いまで。読み進めるうちに、「投資とは何か」「経営とは何か」を再確認できる対話となっています。
1982年大蔵省入省。2018年金融庁長官。 現在、ソニーフィナンシャルグループ代表執行役社長CEO。2021年NVICのアドバイザリーボードメンバーに就任。
1992年日本長期信用銀行入行。長銀証券、UBS証券を経て2003年に農林中央金庫入庫。2007年より「長期厳選投資ファンド」の運用を始める。2014年から現職。
NVICが設立されてから10年が経ちました。私たちは今、企業哲学である「NVIC WAY」をどのように根づかせ、継承していくか。そして、国や社会にどのような価値を提供できるのかを改めて問い直しています。今回は、そのような大所高所の視点からアドバイスをいただくべく、元金融庁長官であり現在はソニーフィナンシャルグループ 代表執行役社長CEOとして活躍されている遠藤さんをお迎えしました。
遠藤さんには、コロナ禍の最中に京都大学での学生向け講義にご登壇いただいたことがあり、京都ラボでも実際にお話を伺う機会がありました。今回は、より深くNVICの今後についてご意見を伺いたいと思い、お越しいただきました。

奥野さんと最初にお会いしたのは、富国生命の米山社長のご紹介がきっかけでした。米山社長は業界内でも非常にユニークな経営者として知られていますが、その米山社長が「自分よりもとんがっていて、気に入っている人物」として奥野さんを紹介してくださったんですね。それを聞いて、私も「ぜひ会ってみたい」と思い、実際にお会いすることになりました。
その後、金融庁でNVICのエンゲージメント活動についてご紹介する機会がありました。資本コストの考え方や投資先企業との対話の進め方など、実務に基づいた具体的な取り組みをご説明しました。また、NVICアカデミーでは、地方金融機関で働く若手行員向けに遠藤さんに講演をしていただき、大変意義のある時間となりました。

金融庁にいた当時も、若手職員や外部の若い世代に向けて話す機会がありましたが、経営層に対する講演が多く、若手や中堅職員と接する場は限られていました。ですから、そうした世代に向けて話せる場では、「今の金融機関のあり方に満足していますか?」という問いかけをするようにしています。そして、もし違和感を覚えるならば、それを正すために自ら何ができるかを考えてもらう。そうした問題意識を持ってほしいと思っています。
現地・現場に赴く
遠藤さんは現場にも足を運ばれる方です。隠岐島の海士町にご一緒したこともありますよね。

長官退官後、顧問として部屋をいただいていたところに奥野さんがいらして、「今度、海士町に行くんですよ」と話されたのがきっかけです。
金融庁での業務では、地方の金融機関と多く関わる機会があり、地域経済を活性化しようとするさまざまな取り組みや、その具体的な事例に数多く触れてきました。そうした中で、大きなテーマの一つが「地方再生」でした。その流れの中で、特に注目していた地域が海士町です。以前から「いつか現地を訪れてみたい」と考えていたのですが、そんな折に奥野さんから海士町の話を伺い、まさに“天啓”のように感じ、ご一緒させていただくことを決めました。
海士町では、金融教育などをテーマに、地域の方々と車座で懇談しましたね。
あの町には全寮制の高校があり、放課後には利用できる塾も整備されています。高校生を地域全体で育てようという意思が随所に見られ、とても印象に残っています。実際、島外からの「島留学」希望者も増えているようです。
かつては廃校寸前だった高校ですが、トヨタやリクルートのOBなど民間出身者が再建を主導し、全国から人材が集まるようになりました。
NVIC アドバイザリーボード
役所を辞めた後は、時間が許す範囲で民間企業のアドバイザーも引き受けようと考えていました。その一つがNVICのアドバイザリーボードです。NVICの皆さんや他のアドバイザーと交わした議論から、私自身も多くを学ばせていただきました。
皆さんが一切の忖度なしに議論を交わしてくれます。農林中金にとっても、これは非常に意義深い場になっていると思います。
ところで、遠藤さんはなぜ金融庁に?

私は1982年に大蔵省に入省しました。当時、大蔵省か通産省のどちらかで働きたいと考えており、幸運にも大蔵省から内定をいただきました。キャリアの初期は主計局で、その後、主税局で課長補佐として所得税・消費税・税務調査など、約10年にわたり税制に関わる業務を担当しました。その後、1990年代後半にはIMF(国際通貨基金)への出向で米国に駐在。グローバルな視点で金融と経済を学ぶ貴重な機会でした。2002年に帰国し、金融庁への配属が実現しました。税や財政のように巨大で抽象度の高い制度設計では、自分の仕事の手応えが見えづらいと感じることがありました。だからこそ、もっと実感を持って取り組める仕事として、金融行政の道を選んだのです。
NISA、ここだけの話
NISAの制度拡充には本当に驚きました。1800万円までの非課税枠、これはすごいです。
NISAはイギリスのISA(Individual Savings Account)をモデルにしたものです。税制改革には必ず党税調や主税局との調整が必要で、通常は「財源はどうする?」という議論になります。ところが、NISAの場合は「新たな経済活動を促す」という前提があるため、本来は税収が減るわけではない。それでも制度創設時には激しい反発を受け、非常に難しいプロセスでした。
しかし岸田政権下で状況が一変します。当時、岸田総理と、英国財務省出向経験がありISA制度にも詳しい木原補佐官の連携によって、「NISAを完成形に」という流れになったものと推察しています。党税調の反対を押し切り、官邸主導で制度拡充が決まったのです。実のところ、金融庁はその決定を事前に知らされておらず、制度が「官邸から降ってきた」感覚でした。それほど強い政治判断が働いたのだと思います。
将来的に岸田さんが名宰相と称されるなら、NISAの制度拡充は間違いなくその一因になりますね。

資産運用立国と金融教育
この取り組みは、前任の森長官の時代から始まりました。当時、森長官が強く問題意識を持っていたのは、日本では預貯金に資金が過剰に偏り、資産運用がなかなか進んでいないという現状でした。
その打開策として注目されたのが「投資信託」でした。中でも、「つみたて」という手法に焦点を当て、預金から投資へのシフトを促そうとしたのです。この流れは、1980年代のアメリカですでに始まっており、イギリスでもISA(個人貯蓄口座)制度が資産形成を後押ししていました。森長官は、日本にもこうした流れを根づかせたいと考え、菅官房長官に「つみたて投資」の必要性を提案。その結果、安倍政権によって「つみたてNISA」として政策に取り入れられました。
日本は長年、労働収入と預貯金で資産形成するという考えが主流でした。資本主義における「資本家としての参加」というマインドセットを教育の中で育ててこなかった。ここに大きな課題があると感じています。
金融庁でも当初は、金融教育を「一つの課の業務」として扱っていました。でも、それでは駄目だと感じ、「全庁的な取り組み」として進めるべきだと考えました。私自身も含め地方出身者も多い金融庁職員がそれぞれの想いを持ち、それを地域に還元することができれば、大きなムーブメントを生み出せるのではないか。金融庁は、24時間、365日、金融のことを考えている人間の集団です。そんな考えから、「母校に帰ろう」キャンペーンを呼びかけました。

我々も丁度その時、高校生向け金融教育を始めようとした時期でして、最初の学校がNVIC職員の母校である城北高校だったんです。その時我々の後のコマで授業を行ったのが彼の高校のクラスメイトでもある金融庁の職員の方でした(笑)
しかし、現実には縦割り行政の実態があり、学校の先生による「お金」の話は、なかなか難しい。文科省との議論はどうなっているのでしょうか。
各省庁はそれぞれ自分たちのテーマを教育に組み込もうと話を持ち込んできます。たとえば、財務省は「税」、農林水産省は「農業」といった具合に、どの省も自分たちの分野に関する内容を教育現場に加えようとしてきます。結果として、こうした提案はすべて文科省に集まってくるのです。そうした状況の中で、金融教育は学習指導要領の改訂により、家庭科の科目の中に盛り込まれることになりました。そういえばNVICも教材を制作されていますよね。
誰かに頼まれたわけではないのですが、独自に金融教育の教材を制作しました。投資信託協会や、教材を実際に使って授業を実施してくれた茨城県の高校と協力して、YouTubeでその授業の様子も発信しています。私たちが伝えたいのは、資本主義社会に「資本家」として参画するという考え方です。これは単なる知識や技術ではなく、まず「心構え」や「マインドセット」を育てることが大切だと考えています。
京都大学での講義と哲学の継承
金融教育という点では、京都大学での経営学講義が非常に印象的でした。学生たちが実際に企業の価値創造を体験的に学べる場であり、講義録をまとめた書籍も非常に優れた内容でした。
この講義は今も継続しており、今年はアシックスの廣田会長をお招きしました。私自身が面白いと感じた経営者に出会えたら、その場で登壇をお願いするようにしています。就職してしまえば他社の経営者の話を聞く機会はほとんどありませんから。
まさにあの講義こそ金融教育の真髄です。企業がどのように価値を生むのかを、学生が肌で感じることができる貴重な機会です。
私は、長く続く事業には「哲学」が必要だと考えています。短期的な成功はあっても、哲学のない事業は長続きしません。
設立趣意書と企業の原点
ソニーといえば、まず思い浮かぶのが、井深大さんが掲げた設立趣意書です。「真面目なる技術者の技能を、最高度に発揮せしむべき自由闊達にして愉快なる理想工場の建設」この言葉には今でも鳥肌が立ちます。言葉の持つ力を強く感じさせられます。ソニーがかつて業績不振に陥っても、そこから復活を遂げられたのは、この理念があったからこそだと私は思います。遠藤さんがソニーグループに加わってみて、どのように感じられましたか?
私も設立趣意書の持つ意味と力を実感しています。戦後の焼け野原の中で書かれたこの設立趣意書は、今もなお、社内で脈々と受け継がれています。2000年代から2010年代初頭にかけて、ソニーは非常に苦しい時期を経験し、「もう終わりではないか」と言われていました。しかし、そんな中で立ち上がったのがエンジニアたちでした。彼らは原点である設立趣意書に立ち返り、「今こそこの理念を実現するべきだ」との思いで社長に直訴したのです。
その結果生まれたのがアクセラレーションプログラムでした。これは、苦しい時期だからこそ長期的な取り組みを可能にしようとするもの。原点にある言葉の力が、ソニーの再生を後押ししたのです。エンジニアの熱意は決して絶えませんでした。原点にある言葉が、企業の行動を支える。それがどれほど重要なことかを感じました。
新しいものを生み出し続ける、その源泉には理念があると私は思っています。NVICにも設立趣意書を設けました。「経世済民」経済の力で日本を元気にしたいという思いです。農林中金の子会社という立場であっても、志を言葉として明文化することが必要だと考えた結果です。私たちの設立趣意書は、こう記しています:「知的生産活動における創意工夫を最大限に発揮せしむる環境を整備する」この言葉は、ソニーに対する尊敬と、我々が目指す組織文化への想いから生まれました。
ソニーフィナンシャルグループとライフプランナーの価値

世界中の卓越した生命保険・金融プロフェッショナルが所属する国際的団体 「Million Dollar Round Table(MDRT)」という組織があります。日本では、生命保険会社の営業職員のうちMDRTのメンバーは平均で3%程度ですが、ソニー生命ではなんと30%以上がMDRTの会員です。
ソニー生命は1979年、米国プルデンシャル生命との合弁会社として設立されました。当時は護送船団方式と呼ばれる行政指導のもと、外資系企業が単独で日本市場に参入することは認められていませんでした。そのため、合弁という形が取られました。その後、1980年代にプルデンシャルは合弁を離脱し、独自で日本市場に進出。結果的に、日本で「ライフプランナー」型の営業モデルを展開しているのは、現在もこの2社のみです。このモデルでは、保険商品を売ることが目的ではなく、顧客の人生全体を見据えた「ライフプランニング」を提供することが核になっており、その結果として保険が販売される、という考え方です。
私が金融庁にいた頃は「それって理想論ではないか?」と懐疑的に見ていたのは事実です。しかし、ソニーフィナンシャルグループに関わるようになってから、その印象は大きく変わりました。現在は、傘下のソニー生命のライフプランナー約5,700人、うち特に優れた約500人のエグゼクティブライフプランナーと直接関わる機会があります。
実際に彼らの営業現場を見て、本当に驚きました。自ら主催する勉強会にも参加させてもらいましたが、そこでは顧客同士の交流を通じて自然な形で信頼関係が生まれていました。ライフプランナーは全員中途採用で、新卒はゼロ。また、保険業界出身者をヘッドハントすることもなく、他業界から人材を採用しています。
印象的だったのは、建設業界出身のライフプランナーが主催する勉強会です。
彼は、地方の工務店や大工さん、左官職人といった地元で活躍する方々を顧客として迎えていました。そして、自腹で費用をかけてその顧客たちを集め、勉強会を開催していたのです。この勉強会では、参加した顧客同士の間で「化学反応」とも言えるような交流が自然と生まれていて、その様子は本当に驚くべきものでした。
特に印象的だったエピソードがあります。勉強会の途中、主催者であるライフプランナーが一時的に席を外していたのですが、その隙に、参加者の一人が私のもとにやって来て、主催者が自分にとってどれだけ大切な存在かを熱く語ってくれたのです。その方は、「これまで一度も保険の勧誘をされたことがない」とも話していました。彼(=ライフプランナー)は、保険を売る前にまず、顧客の悩みや課題に真摯に向き合ってくれる。その姿勢が信頼につながり、「あなたが提案する保険なら入りたい」と、顧客の方から申し出るのだそうです。この話を聞いて、私は心から納得しました。顧客の課題を知り、その解決に本気で取り組む。その徹底ぶりこそが、顧客からの深い信頼につながっているのです。
これこそが「顧客本位の業務運営」の本質だと、あらためて実感しました。利他的に行動しながらも、確かな成果を出している。そんな人たちがこれほどいるという事実に、深く驚かされました。
私も農協職員の方々と全国でお会いすることが多く、「人生の相談に乗ってください」とよく伝えています。高齢化や後継者問題など、組合員の方々は多様な悩みを抱えています。その一つひとつに丁寧に向き合うことで、結果的に金融サービスが必要となる場面が生まれます。お客様に寄り添うことで、自然と商品が選ばれる。これは農協という組織だからこそ実現できるスタイルだと思っています。

ソニー生命のライフプランナーは雇用形態は正社員ですが、個人事業主的に働いており、その点で「特殊」と言えるかもしれません。彼らの収入は事業所得で、フルコミッション制。つまり、生命保険の売上高によって決まります。私自身、金融庁に在籍していた頃は、このフルコミッション制に対して否定的な見方をしていました。しかし、実際にソニー生命は顧客満足度の高い企業として知られています。なぜ彼らが高い顧客満足を得られているのか。今の私の考えでは、それは「フルコミッション制」という報酬の仕組みそのものではなく、「独立自営」という働き方に理由があるのだと思います。
ライフプランナーは、上からの指示に従うのではなく、自分の判断で、目の前の顧客にとって本当に必要なことを提案できる。自ら考え、工夫し、行動できる環境があるのです。実際、中途採用で入社したライフプランナーの多くは、以前の職場で「このままではお客さんのためにならない」というジレンマを感じていた人たちです。ソニー生命ではノルマがなく、独立自営であるがゆえに、目の前の顧客一人ひとりにしっかりと向き合うことができるのです。
さらに特筆すべきは、ソニー生命の経営サイドにはライフプランナーに対する人事・評価権がないという点です。評価はすべて顧客からの信頼と実績に基づきます。トップライフプランナーが一堂に会する全国大会では、社長や幹部は主催側ではなく招かれる側となり、主役はあくまでライフプランナーです。まさに「逆ピラミッド型」の組織です。
独立自営という形は、次世代の組織設計における重要なヒントになると感じています。


私もそう思います。ノルマで縛るのではなく、裁量を与える。それを本気で貫けば、組織文化は必ず変わるはずです。
最後に、少し視点を広げてお伺いしたいのですが、日本を元気にするには、どのような施策が必要だとお考えでしょうか?
正直に申し上げて、税制や金融政策の変更だけで日本が元気になるとは思っていません。やはり鍵を握るのは、民間の経済活動がいかに活性化するかだと考えています。そのためには、まず働く一人ひとりが「自分の仕事が面白い」「自分は良い仕事をしている」と実感できることが重要です。そう感じられない環境では、創造性も成果も伸びていきません。ノルマに追われるだけの働き方や、気持ちが入らないまま続ける仕事では、限界があるのです。
これから求められるのは、内発的な動機づけです。ワクワクしながら働ける社会をどうつくるか。それを支えるのが、企業のガバナンスや、投資家のあり方でもあると私は思います。「お客様のために自分は何ができるか」「会社や社会にどう貢献できるか」。社員一人ひとりがそう考え、行動できるようになれば、日本はもっと元気になる。私は心からそう信じています。
あとがき
遠藤さんとの対談を終えて、私たちは多くの気づきを得ました。印象的だったのは、「人が自ら考えて動けるかどうかが、日本の元気に直結する」という言葉です。これはNVICの根幹にある思想とも重なります。知的生産に携わるすべての人が、自らの創意工夫を発揮できる環境をどう整えるか。その問いは、私たち自身にも常に投げかけられています。また、ソニーの設立趣意書にあるように、言葉は組織の未来を形づくる力を持ちます。NVICもまた、「経世済民」という志のもとに、次の10年をどう描くか。
今回の対話は、その羅針盤の一つとなりました。これからも、お客様、投資先、地域社会、すべてのステークホルダーと誠実に向き合いながら、私たちの存在意義を磨いていきたいと思います。ここまでお読みいただき、ありがとうございました。