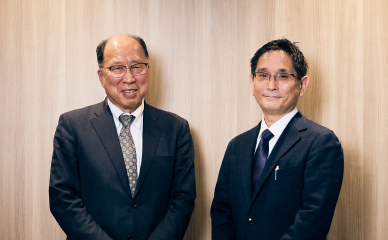2000年代後半、長期厳選投資という考え方は、まだ広く浸透していませんでした。そんな時代にあって、この投資哲学を出発点として運用を展開していったのが、農林中金バリューインベストメンツ(NVIC)です。
本対談では、その創成期から現場で歩んできたメンバーが集い、年金基金向け営業の立ち上げ、リテール個人向け商品の展開、そして投資家との信頼関係をいかに築いてきたかをはじめ、NVICのこれまでの事業展開の節目になった出来事について語ります。NVICが何を大切にし、どのような道のりを歩んできたのか。その軌跡を振り返るひとときとなれば幸いです。
1996年日本長期信用銀行入行。2002年農林中央金庫入庫。農中信託銀行への出向、JAバンクリテール実践部副部長、全農営業部長などを経て、2025年より常務執行役員。
1992年日本長期信用銀行入行。長銀証券、UBS証券を経て2003年に農林中央金庫入庫。2007年より「長期厳選投資ファンド」の運用を始める。2014年から現職。
1999年三和銀行(現三菱UFJ銀行)入行。国内外証券を経て2009年に農中信託銀行入行。ロンドン留学後、2018年にNVICに出向。
NVICの歴史を紐解き共有しようというシリーズ「NVIC History」。2007年から始まった年表には様々なイベントが記されていますが、その中でも2009年、2010年にフォーカスし、農中信託銀行でゼロから年金基金向けの営業を立ち上げていた時期に深く関わった爲井さんをお迎えし、当時の出来事についてお話を伺います。
まさかこのような場所でお話しするとは思っていませんでした(笑)。まず自己紹介をさせてください。2002年に日本長期信用銀行から農林中金に移り、札幌支店を経て2006年に農中信託銀行に異動しました。当時の主な業務は、ヘッジファンドやプライベートエクイティ(PE)ファンド等の運用受託営業でした。その中で、奥野さんのチームが手がけていた「オアシスバリューファンド」の営業を担当することになり、全国を一緒に回ったのが最初の接点です。
その後、JAバンクで投資信託を本格的に扱うプロジェクトに関わり、「おおぶね」シリーズの窓口販売を担当する中で、再び奥野さんたちとご一緒することになりました。

JAバンクとの協業は2017年、2018年ごろでしたかね?
はい、そのころです。その後は農林中金の貸出部門に異動しましたが、NVICとは離れてはまたつながる、という関係が続いています。不思議なご縁を感じています。
正直に言えば、爲井さんがいなければ、今のNVICは無かったかもしれません。「おおぶね」がJAバンクのセレクトファンドに入ったのは、爲井さんのご尽力があってこそでした。


さまざまな場面でいつも爲井さんに助けていただいている印象があります。
年金営業の開始と長期厳選投資への挑戦
2009年当時の農中信託、私が丁度入社した時だったのでそう思っただけかもしれないですが、今思うとあの時は「いい時代」だったのではないでしょうか?
そう言っていただけるのは嬉しいですが、長原さんが入社した2009年当時はまだ年金基金向け営業は後発中の後発でした。投資一任の免許を取ったばかりで、当初はまず小さな実績を積み重ねるところからと考えていました。ところが思いがけず、非常に規模の大きな案件が舞い込み、プロダクトはヘッジファンドでしたが、ありがたくもそのご縁から、2,000億円規模の受託に成功し、農中信託の年金基金向けビジネスが本格的にスタートすることになりました。
2007年の奥野チームが農林中央金庫で立ち上がった頃から、爲井さんと奥野さんの接点はあったのでしょうか。
その時点では、まだ爲井さんとは直接の関わりはありませんでした。私は2003年に農林中金に入社し、しばらくはプライベートエクイティやヘッジファンドへの投資業務を担当していました。その後、「アルファ株式運用チーム」という構想を提案したことをきっかけに、株式投資部へ異動し、以降は酒見さん(現在はNVIC代表取締役社長)とともに仕事をするようになりました。社内での株式投資の運用を持続・発展させるには、外部資金の受け入れが不可欠だと考えており、そこから爲井さんとの接点が生まれていきました。
「何をしているの?」と聞かれ、「年金基金向けにオルタナティブのファンドを提供しています」と答えたのが接点のきっかけでしたね。それから奥野チームのファンドを私の営業先に提案する流れになりました。

当時は、「長期厳選投資」というコンセプト自体が、ほとんど理解されていませんでした。年金基金などの運用方針として一般的だったのは、「株式投資はリスクを低減させるためにできるだけ広く分散させるべき」という考え方。いわばインデックスに近い運用が推奨され、アクティブ運用であっても、安くなったら買い、高くなったら売るという銘柄の入れ替えを繰り返す、いわゆる「回転型」のスタイルが主流でした。そんな中で、「長期厳選投資」という考え方を年金運用の現場で理解していただくのは、非常に難しかったですよね。
ものすごく大変でした。二十数企業のポートフォリオと説明すると「これじゃあパフォーマンスを出せるわけないでしょ?」という反応ばかりでした。なぜ集中させるの?リスク高いでしょ?そんな決めつけのような感じでした。
株式の長期厳選投資という提案はそもそも聞いてもらえないことが多かった。20人に話しても、関心を示してもらえるのはたった2~3人ぐらい、というのが実感でした。
初期の苦労と嵐の中のプレゼンテーション
私が2009年に農中信託銀行に入社したとき、奥野チームは1階オフィスフロアの端にいましたよね?
はい、ほとんど用務室のようなスペースでした(笑)。

私は入社したばかりだったので何も知らずに、最初の印象は「この人たち、ひょっとして窓際族なんじゃないか…?」というものでした(笑)。全体の会議中に英字の経済紙(FT)を堂々と思いっきり広げて読んでいる人もいて、かなりヤバい人がいるなあと思っていました。
それ、私ですね。カッコつけてました(笑)
その後、当時の農中信託の社長(安田社長)から「面白いファンドがある」と紹介されて、奥野チームのファンド説明会に参加しました。その説明会で奥野さんがめちゃくちゃ熱くお話しされていたのですが、「長期厳選投資」というファンドの哲学に触れて、これは直感で面白いと思ったんです。説明会のすぐ後、顧客を訪問して提案してみようと思いました。これは絶対ニーズがあると。
たしか、その後一緒に出張して、鉄道関連会社などを訪問しましたよね。
はい、そのときはどこも導入には至りませんでした。ただ、岡山のある先進的な年金基金担当者との面談が印象的でした。その方は業界で著名な方で、奥野さんが「コンサルが年金に持ち込んでいる資産配分の考え方とか投資戦略がそもそも良くないですね」と言ったところ、「私、元コンサルだけど何か?」と返されて、場が凍ったのを覚えています(笑)。それでも、数年後にはその方が我々のファンドに投資を決めてくれたのは奇跡としか言いようがないです。個人的にもまだお付き合いをさせていただいていますし、不思議な縁ですよね。
某大手電機メーカーとの商談
そして次に向かったのが、国内の大手電機メーカーの年金部門でした。爲井さんも一緒でしたよね?当時の担当者は「瞬間湯沸かし器」と言われるほどの怖い人で知られていて、少しでも失礼があれば即出禁になるという噂もあり、訪問させて頂く際はいつも緊張感のあるミーティングでした。最初はディストレスファンドをご紹介していたのですが、その担当の方から「日本株のファンドを紹介して欲しい」と求められ、そこで奥野さんのファンド「オアシスファンド」を提案したんです。提案は割とうまく運び、首尾よく最終決裁者(常務理事)へのプレゼンテーションまで何とか漕ぎつけました。
常務理事へのプレゼンの日は、ちょうど嵐の日でしたよね。横殴りの風と雨のなか、3人でプレゼンに向かったのをよく覚えています。
会議では、常務理事がさまざまな質問や意見を奥野さんに投げかけ、それに対して奥野さんは毎回「お言葉を返すようですが」と結構ストレートな物言いで応じていました。まさに真剣勝負のようなやりとりだったと思います。
そのやり取りの最中、私はふと「お二人は、実は同じことを言っているのではないか」と気づいたんです。それを思い切って口にしたことで、会議の空気が少し和らいだのをよく覚えています。会議が終わった頃には、外の嵐もまるで今まで何もなかったようにすっかり止み、青空が広がっていました。嘘のようなホントの話なんです。

あの時間帯だけ、まさに嵐だったんですよね。
最終的には何とか投資してもらえましたが、金額は減額となりました。先方からは「お言葉を返し過ぎたんだよ」と冗談交じりに言われました(笑)。
大手年金基金への広がり
その後は、大手ハウスメーカーや自動車部品会社など、いくつかの年金基金にも提案を重ねていきましたよね。
2010年ごろからですね。大手電機メーカーの後、大手ハウスメーカー、自動車部品企業と受託が広がっていきました。
ただ、年金ビジネス全体としては赤字続きで、厳しい時期でしたよね。
「格付けが無いと投資できない」との声があったので、R&Iやラッセル、マーサーといった機関に評価を依頼しました。おかげで徐々に信頼が広がっていきました。
そうした中、自動車部品メーカーからの受託が大きな転機になりましたよね。
はい。採用がほぼ決まりかけた段階で、「信託報酬を引き下げてほしい」と要望がありました。当時、農中信託では信託報酬を下げた前例がなかったので苦労しました。
でも、ここで断ったら、自社の運用哲学が年金業界に広がる可能性を潰すことになる。しかもこの案件は数十億円。既存の受託額を大きく上回るインパクトでした。
社内での会議もかなり白熱しましたよね。
年金業界でのステータスをここで取りにいくんだという方向性を考えると、これを取りに行かないという選択肢は無かったんです。これを通せないのであれば、もうこのビジネスはやらない方がいいと。 幸いなことにその後無事受託が決まりましたが、今振り返っても、あの覚悟と判断がなければ「おおぶね」や長期厳選投資の広がりは実現していなかったかもしれません。

リテールへの展開とおおぶねの成長
私は当初リテール個人向けのファンドを本格的に展開するという考えはあまり持っていませんでした。長期投資を担えるのは、何だかんだ言って大きな資金を持つ企業年金をはじめとしたプロ機関投資家だと思っていたからです。
ただ、2017年にSBI証券で「おおぶね」がiDeCoの対象商品として採用されたことで、その考えが変わりました。企業年金ビジネスもよく考えると、究極的には「働く個人の資産の集合体」です。であれば、むしろ個人こそが真の長期投資の主体ではないかと気づかされたのです。
JAバンクでの投信窓販も、ちょうどその頃から本格的に加速していきました。私が異動してきた当初は、まだまだこれからという状況でしたが、最初の会議で「大きな飛躍を目指す」というビジョンが示され、目標も与えられたのですが、「その目標は桁が違うのでは…?」と思わず心の中でつぶやいたのをよく覚えています。
当時、JAにおける投資信託販売は新たなチャレンジの段階にあり、「どのようにすれば、より確実にお客様にご案内できる体制を築けるか」を考えました。そこで、証券会社での豊富な経験を持つ人材を新たに迎え、JAとの連携による同行営業の体制を整備しました。人員体制の構築には一定のコストを要しましたが、「地域の皆さまに安心して投資を始めていただける仕組みが必要だ」との思いで社内の理解を得ることができました。
その後、全国のJAと二人三脚で取り組む中で、おかげさまで販売残高も着実に伸長しています。
あるエリアのJAでは、「おおぶね」の販売比率が非常に高くなっており、私自身も驚きました。その背景には、大手証券会社出身の担当者が「これは信頼できる商品だ」と確信を持ち、現場で熱意を持って広めてくださっているという話を伺っています。
証券会社で回転売買を経験してきた方たちが「おおぶね」を見て、「これだよね」と納得してくれたのが印象的でした。米国への株式投資で、しかも選び抜かれた米国企業への長期厳選投資。証券会社の方にとっても納得感が高いのです。
投資哲学で選ばれるファンド

ここまでの話を振り返ってみると、ファンドを選んでくださったお客様には、共通した何かがあるように思います。
そうですね。私たちが目指していたのは「納得感かつ手触り感のある運用」。単に目先の数字を追うだけでなく、企業の本質を見て、それに共感できる人たちと繋がっていきたいと思っていました。
実際に、年金基金の担当者からは「プライベートエクイティ的な視点で見ている」「これは上場株というより未上場企業への投資に近い感覚だ」と言ってくださった方もいらっしゃいました。

ファンドの哲学そのものに共感してくださった方が多かったですね。その後似たようなコンセプトのファンドが後から出てきましたが、「奥野さんがやっていることを長期投資の特性を理解して、共感できるかどうか」という判断基準で選んでくださる方が、少しずつ増えていったと感じています。
まさに「株式投資の原点に戻る」という感覚でしょうか。売ったり買ったりの短期取引ではなく、企業の本質的な価値に目を向け、それを信じて預ける。そうした原点に立ち返る機会になったという声を、いくつもお客様からいただきました。
私たちは、お客様向けに年次総会を開き、投資先企業の工場見学を行っています。実際に現場を見ていただくことで、「自分のお金がどこに流れていて、世の中にどのような価値を提供しているのか」を実感してもらえる。そうした手触り感があることで、長期投資は続けられると思うのです。
2011年3月11日の東日本大震災の際には、週明けにいち早く「どの企業のどの工場が被災しており、どのような状態になっているのか」を調べたA3一枚のレポートを作り、年金のお客様にお渡ししました。不安が広がるなかで「自分の投資している資産は今どうなっているのか」を説明するのは、運用者の責任だと思っています。
一般的な運用会社では、営業、運用、バックオフィスが完全に縦割りです。でも、お客様にとってはそんなことは関係ありません。だから私たちは、アナリストにも年次総会に出てもらうし、現場で説明もしてもらう。運用と営業を分けない。それが私たちのスタイルです。運用だけやりたい、分析だけやりたいという人には、正直うちの会社は向いていません。誰のために、何のために運用しているのか。お金を預けてくれている人に対して価値を届けるという視点を忘れたら、NVICの存在意義はなくなってしまいます。
私自身、これまでのキャリアの中で、常に「どうやったらできるか?」という問いを自分に課してきました。「やらない理由」って、実は簡単に出てくるんですよね。でもそんなことばかり言っていると、前には進めなくなる。「できない理由を探すのではなく、どうやればできるかを考えよう」とチームにいつも呼びかけるようにしています。そうすると、メンバーから思いがけない提案が出てきたりする。これは、NVICのヒストリーそのものにも通じる考え方だと思っています。
自動車部品メーカーからの受託も、その象徴でしたね。
あの時は「ここを通さなければこの仕事に未来はない」という覚悟で臨んでいました。ああいう場面で強く出ると、当然、結果には責任が伴います。でも、その覚悟を持てたからこそ、次の展開に繋がっていく。本当にそう思います。
何かを変えようとするなら、それができないくらいなら退路を断つぐらいの「覚悟」が必要だと思います。無理難題を通すには、それくらいの熱量が必要だということを、私たちは体感してきました。
あとがき
NVICの歩みは、投資哲学への共感から始まりました。現場で語り、問いかけ、共に考えるなかで、年金基金のご担当者、JAの窓口で真摯にお客様と向き合う職員の方々、長期的な視点で資産形成に取り組む個人投資家の皆さまとの間に、少しずつ信頼の輪が広がっていったのだと思います。
いかなる環境下でも企業の価値を見極める眼差しを持ち、丁寧に言葉を重ねていく。その姿勢に共鳴してくださった投資家の方々が、今のNVICをつくってくださいました。これからの資本市場においても、私たちが大切にしてきた「長期的な信頼の積み重ね」や「本質を見つめる視点」が、日本の投資文化をより豊かなものにしていくと信じています。